最近のフォルクスワーゲンやアウディでは、レバー式のサイドブレーキに代わり、スイッチ操作で作動する 電動パーキングブレーキ(EPB) が主流となっています。
利便性や安全性の面で優れたこの機構ですが、水没・バッテリー上がり・制御系の故障などが発生すると、ブレーキが解除できず車両を動かせなくなるという問題が起きる場合があります。
こうしたトラブル時、牽引や積載車での移動も難しく、現場対応が求められることがあります。
本記事では、VW Golf 7を例に、EPBを手動で解除する方法とその仕組みを詳しく解説します。
また、解除後に必ず行うべき「基本調整(初期化)」についても触れ、再発防止と安全確保の観点から正しい整備手順を整理します。
参考リンク:ナイルメカチャンネル「電動パーキングブレーキを手動で解除する方法(VW・Audi共通)」
▼ナイルプラスのサービス詳細▼
電動パーキングブレーキの仕組み
EPBとは何か
電動パーキングブレーキ(EPB:Electric Parking Brake)は、近年のVolkswagenやAudiなどに広く採用されている電子制御式のサイドブレーキです。
従来のようにレバーやペダルを引くのではなく、スイッチ操作でブレーキが作動します。
ドライバーはボタンを引くだけで、後輪のブレーキキャリパー内に内蔵されたモーターが動き、ピストンを押し出してブレーキを固定する仕組みです。
従来のワイヤー式との違い
昔ながらのサイドブレーキは、レバーやワイヤーを通して人の力でブレーキパッドを押し付ける構造でした。
これに対してEPBは、小型モーターがピストンを直接駆動します。
ワイヤーがなくなることで、設計の自由度やキャビンスペースの確保が向上し、制御精度も高まりました。
また、運転支援システムとの連携が容易になり、たとえば「オートホールド(停車保持)」機能などにも応用されています。
制御ユニットとの連動
EPBは単なるスイッチではなく、電子制御ユニット(ECU)とブレーキキャリパーが常時通信しています。
運転中の速度やギア位置、ブレーキ踏力などの情報を元に、作動を自動で判断するため、誤操作による急ブレーキを防ぐ仕組みです。
また、シフトレバーが「Pレンジ」に入ると自動的に作動するよう設定されている車も多く、電源が入っている限りは安全に作動・解除を繰り返せます。
モーター駆動のメリットと注意点
EPBは人の力に頼らず、ボタンひとつで確実にブレーキを保持できるという利点があります。
一方で、モーターと電気信号に依存する構造であるため、バッテリーが上がったり電気系統が故障すると、ブレーキが「解除できない」状態に陥ることがあります。
この「動かせない状態」がEPBトラブルで最も多いケースです。
👉VW ブレーキトラブル総合ガイド|症状・原因・修理費用・関連整備が全部わかる記事
なぜ「動かせなくなる」のか
電源が遮断されると作動不能に
EPBは、モーターの力でブレーキキャリパー内のピストンを押し付け、ブレーキを固定する仕組みです。
つまり、電気の力で作動・解除を行うシステム。
そのため、バッテリーが上がって電源供給が止まると、解除信号を送ることができなくなります。
ブレーキは締まったままの状態でロックされ、車を押してもタイヤが回らず、結果として「動かせない」状況になります。
主な原因
代表的な原因は以下の3つです。
- バッテリー上がり:冬場や長期放置などで電圧が低下し、EPBユニットへの電源が途絶。
- 水没・浸水:ハーネスやコネクタ部分がショートし、モーターへの信号が届かない。
- モーター故障:キャリパー内のモーター自体が焼損・固着して動かなくなる。
特に近年の車は電装品が多く、バッテリー上がりが発生するとEPBだけでなくシフト制御やパワステなども同時に停止します。
トランスミッションの構造上の問題
さらに、EPBトラブルを厄介にしているのがトランスミッションのPレンジ構造です。
Pレンジではトランスミッション内部でロックピンがかかり、駆動輪が完全に固定されます。
そのため、ブレーキと駆動輪の両方がロックされた状態になり、物理的に車を押したり牽引したりできません。
たとえシフトをN(ニュートラル)にしたくても、電源が入らなければシフトロック解除ボタンが反応せず、解除操作ができないことが多いのです。
レッカー移動が難しい理由
このようにEPBとPレンジの両方が作動していると、タイヤが完全に固定されたままになります。
レッカー車のウインチで引っ張っても動かず、無理に引きずるとドライブシャフトやトランスミッションを損傷する危険があります。
そのため、レッカー業者も慎重な対応を求められます。
こうしたトラブルを安全に解決するには、電気を使わずに機械的にブレーキを解除する方法を理解しておく必要があります。
緊急時の応急措置
- モーターの取り外し
モーターは通常、リアブレーキキャリパーに取り付けられており、トルクス30の2つのネジで固定されています。
これらのネジを外してモーターを取り外します。 - モーターの逆回転
モーターを外した後、内部の星型ギアをプライヤーで逆回転させます。これにより、ブレーキピストンが戻り、ブレーキが解除されます。 - 安全対策
モーターを外した状態で車両を動かす場合は、必ずパーキングに入れてください。
また、修理が完了した後は、ブレーキシステムの再調整が必要です。
電源が完全に入らない場合でも対応可能
EPB(電動パーキングブレーキ)は通常、電気的な制御によって作動・解除を行います。
しかし、バッテリーが完全に上がってしまった場合や水没などで電源供給が絶たれたときでも、モーターを外して機械的に解除すれば車を動かすことが可能です。
この手動解除方法は、整備工場だけでなく、災害や浸水、長期放置時のトラブルにも役立つ「最後の手段」として覚えておくと安心です。
バッテリー上がり時の効果
バッテリーが上がると、EPBスイッチを操作してもモーターが動かず、ブレーキが締まったままになります。
この状態で車を動かそうとすると、駆動輪が完全に固定されたままになり、押してもびくともしません。
そんなとき、モーターを外してピストン軸を手動で回せば、電源が復旧していなくても機械的に解除可能です。
これにより、車を押して安全な場所まで移動させたり、レッカー車へ積み込むことができます。
水没・浸水時の応急処置
近年では、豪雨や冠水によるトラブルで車両が水没するケースも増えています。
EPBの制御ユニットは電気部品のため、水没するとショートして作動不能になることがあります。
そのような場合でも、モーターを外して手動解除すれば、車体を安全な位置に避難させることが可能です。
ただし、電気配線が濡れたままの状態で通電すると二次的な故障を招くため、応急処置後は速やかに整備工場で洗浄・乾燥・診断を受けることが重要です。
長期放置車の移動にも有効
数カ月以上動かしていない車では、バッテリーが自然放電してEPBが解除できないことがあります。
この場合も同様に、モーターを外してピストン軸を手動で戻せば、一時的に移動が可能です。
ガレージや駐車場での位置調整にも活用できます。
応急対応の限界
あくまでこの方法は「動かすための一時的な手段」であり、修理や走行を目的としたものではありません。
ブレーキが解除されたままの状態で放置すると、転動事故の危険があるため、移動後は必ず輪止めを使用し、早急に修理を依頼してください。
だから選択肢は3つ
こんなとき、VWオーナーにできる現実的な選択肢は次の3つです。
① まずは診断・見積もり
輸入車に強い整備士が原因を特定し、必要最小限で提案。
② 高額修理の前に査定
整備履歴・社外パーツまでプラス査定の外車専門。
③ 修理費リスク回避の“定額で新車”
車検・税金・メンテ込の月額で故障ストレスから解放。
ワンポイント
「走れるから大丈夫」と思っても、実際はいつ爆発するか分からない爆弾を抱えている状態です。
早めに動くほど、費用もダメージも抑えられます。
解除作業の前準備
安全を最優先に
EPBが作動したままの状態で解除作業を行う際は、まず安全確保が最優先です。
ブレーキが効いているとはいえ、車両が不安定な場所にあると転動の危険があります。
必ず平坦で安定した場所に停車し、できれば舗装面で作業を行いましょう。
前後のタイヤには輪止め(チョーク)をかけて、万が一の動きを防ぎます。
シフト操作と電源状態の確認
電源がまだわずかに残っている場合は、作業前にシフトをPレンジに入れておくのが理想です。
Pレンジで固定しておけば、解除中に車が動き出すリスクを抑えられます。
ただし、バッテリーが完全に上がっている場合は、シフトロック解除ボタンを押してNレンジに入れておく方法もあります。
電源状態を確認しながら、作業しやすい位置にシフトを合わせましょう。
必要な工具
EPBの手動解除を行うには、以下の工具が必要です。
- トルクスレンチ(T30):モーター固定ボルトの取り外しに使用
- プライヤーまたはモンキーレンチ:ピストン軸を回すために使用
- 延長バーまたはラチェットハンドル:狭い箇所にアクセスする場合に便利
- 懐中電灯:暗所でモーター位置を確認するため
特にリアキャリパー付近はスペースが限られており、工具の長さや角度が作業のしやすさを左右します。
作業対象箇所
EPBのモーターは、リアブレーキキャリパーの後端部に取り付けられています。
丸型のモーターケースに配線コネクタが接続されているのが目印です。
モーターを直接外すことで、内部のピストン軸にアクセスできます。
作業を始める前に、左右どちら側のブレーキを操作するかを明確にし、周囲のパーツや配線を傷つけないように注意しましょう。
準備が整ったら
車両の安定、シフト位置、工具の準備が完了したら、いよいよEPBモーターの取り外し作業に入ります。
次章では、モーターの構造と取り外し手順を順を追って解説します。
モーターの取り外し手順
モーター位置の確認
EPB(電動パーキングブレーキ)のモーターは、リアブレーキキャリパーの後端部分に取り付けられています。
丸みを帯びた黒いプラスチック製のユニットで、配線コネクタが接続されているのが特徴です。
まず、配線を無理に引っ張らないよう注意しながら、モーター本体の位置を目視で確認します。
右側・左側で取り付け位置が少し異なる場合があるため、事前に両側を確認しておくと作業がスムーズです。
コネクタの取り外し
モーターを分離する前に、電源コネクタを外す作業を行います。
ツメを押し込みながら引き抜くタイプが多く、無理に力を加えるとコネクタが割れる恐れがあります。
固い場合はマイナスドライバーで軽くこじるようにして外します。
コネクタが外れると、モーター部への電気供給が遮断されるため、誤作動を防げます。
トルクスボルトの取り外し
次に、モーターを固定しているトルクスボルト(T30)を2本外します。
ボルトはキャリパー後部に対して左右対称に配置されています。
作業スペースが狭い車種(特にAudi A4系・Golf7系)では、延長バー付きのラチェットハンドルを使うとアクセスしやすくなります。
ボルトを取り外した後、モーターを手前に引き抜くと、キャリパー側に金属製の軸(ピストン駆動軸)が見える状態になります。
モーター分離後の注意点
モーターを外した時点では、まだブレーキは解除されていません。
内部のピストンは押し込まれたままの状態で、キャリパーがブレーキパッドを強く押さえつけているためです。
モーターを外すだけでは解除されないことを理解しておきましょう。
この段階で、モーター軸の奥にある「星型」または「12角」の軸を手動で回すことで、初めてピストンを戻し、ブレーキを開放することができます。
次章では、この手動解除の実際的な操作手順について詳しく解説します。
手動解除の実際
軸の構造と形状の違い
モーターを外すと、キャリパー本体の中央に金属製の回転軸が見えます。
ここがブレーキピストンを直接動かす部分であり、EPBがモーターで回転させていた軸です。
車種によって軸の形状が異なり、VolkswagenのGolf7系などは星型(6角状)、Audi A4やA6などの一部車種では12角形になっています。
どちらも工具の形状が合わないと滑ってしまうため、確実にフィットするプライヤーやトルクスレンチを使用しましょう。
手動で回してピストンを戻す
軸を時計回り(右回し)に回すと、内部のピストンが引き込まれ、ブレーキパッドがディスクから離れます。
これが手動解除の工程です。
反時計回りに回すと再び締め付ける方向になるため、誤って逆に回さないように注意が必要です。
固着している場合は、少しずつ力をかけながらゆっくり回転させましょう。
内部のギアは樹脂製であることも多く、無理な力を加えると破損する恐れがあります。
解除できたかの確認方法
数回(おおよそ10〜15回転)ほど軸を回すと、ピストンが十分に戻り、ホイールを手で回せるようになります。
この時点で車両が自由に動かせる状態となります。
両側を同じように解除しておくと、牽引や押し出しがスムーズに行えます。
もし片側だけ戻らない場合は、内部ギアの噛み込みやピストンの固着を疑い、無理に回さず専門工場で確認してください。
作業のコツ
軸を回すときは、プライヤーを強く挟みすぎず、軽い力で安定して回すのがポイントです。
トルクスビットを差し込んでラチェットで回す方法もありますが、力をかけすぎると軸先端を削ってしまうことがあります。
解除後は、ホイールを軽く回してブレーキが完全に離れているか確認します。
少しでも抵抗がある場合は、ピストンの戻り不足か、パッドが引きずっている可能性があります。
操作後の状態
この時点でブレーキは解除されていますが、当然ながらサイドブレーキ機能は失われた状態です。
車両が転動しやすくなるため、次章で説明するように必ず輪止めを使い、安全な固定を行ってください。
普段は国産車をメインに扱う整備工場でも、こうした欧州車整備の手順や注意点を知っておくと、受け入れの幅が広がります。
輸入車対応を視野に入れて現場の環境を整えるなら、整備用品や作業環境アイテムを幅広く扱う「ヨロスト。」をチェックしてみてください。
配線・バッテリー・エンジンオイルなど、どのメーカー車種でも役立つアイテムがそろっています。
初めての方でも扱いやすい商品が多いので、DIYメンテナンスの第一歩にもおすすめです。
解除後の注意点
サイドブレーキが効かない状態になる
手動でEPBを解除すると、ブレーキピストンが引き戻された状態になります。
つまり、後輪のブレーキパッドがディスクに押し付けられておらず、サイドブレーキが完全に効かない状態です。
このままでは車両が動いてしまう危険があるため、作業後は必ずPレンジ固定または輪止めを使用して安全を確保してください。
坂道や傾斜地では、念のため前後両輪に輪止めをかけるのが理想です。
走行は厳禁
解除した状態のまま走行することは絶対に避けてください。
ブレーキピストンが戻った状態では、制動力が一切発生しません。
走行中に停車できなくなる恐れがあり、非常に危険です。
あくまでこの手動解除は「車両を少しだけ動かすための応急措置」であり、走行目的では使用しないという点を理解しておきましょう。
牽引・移動時のポイント
ブレーキが解除できたら、車両を安全な場所まで短距離のみ移動させます。
可能であれば押して移動するのが理想で、牽引する場合もゆっくりと慎重に行います。
特に自動車運搬用のレッカー車に積み込む際は、タイヤの回転を確認しながら作業してください。
ブレーキが完全に解除されていない状態で無理に動かすと、キャリパーやローターを傷めることがあります。
電源を入れないまま放置しない
モーターを外した状態のまま放置すると、キャリパー内部にホコリや湿気が侵入しやすくなります。
応急処置後はできるだけ早くモーターを仮付けするか、開口部に養生テープなどで一時的に防塵対策を施してください。
また、電源が回復した際には誤作動を防ぐため、すぐに点火ONにせず、まずはモーター接続を確認するのが安全です。
修理・再調整への準備
車両を安全な場所まで移動させたあとは、修理工場でEPBモーターの再装着と初期化を行う必要があります。
モーターを外したままでは警告灯が点灯し続けるほか、制御ユニットが正しいブレーキ位置を認識できません。
次章では、この再設定作業「基本調整」について詳しく説明します。
修理後に必要な「基本調整」
モーターを再装着しただけでは不十分
EPB(電動パーキングブレーキ)のモーターを交換または取り外し・取り付けした後、そのまま電源を入れても正常には作動しません。
内部のピストン位置(押し出し量)が制御ユニットに記憶されていないため、ブレーキを作動させても動作範囲がずれてしまうことがあります。
このずれを修正するために行うのが、「基本調整(初期化)」または「サービスモード設定」と呼ばれる作業です。
基本調整の目的
基本調整では、ブレーキキャリパー内のピストンをモーターでいったん最大まで押し出し、その後に適正位置まで戻すことで、ECUが「いまのピストン位置=基準点」として再登録します。
これにより、モーターとキャリパーの動作が再び同期し、ブレーキの効きが安定します。
この手順を省略すると、ブレーキが過度に締まりすぎる、またはパッドがディスクから離れすぎて効かないなどのトラブルが発生することがあります。
診断機を使った初期化手順
多くの車種では、診断機(VCDSやODISなど)を使用して以下の手順を実行します。
- イグニッションONにする(エンジンはかけない)
- 診断機で「EPB」または「ブレーキ」メニューを選択
- 「基本設定」または「サービスモード」を起動
- 指示に従い、キャリパーを開放 → 閉鎖の動作を自動実行
- 完了メッセージを確認し、エラーコードがないことをチェック
これでECUが新しい位置情報を認識し、通常通りの作動が可能になります。
手動調整が必要な場合
診断機が使えない場合や、旧型のEPBシステムでは手動による初期設定を行うこともあります。
モーターを取り付けた状態でブレーキペダルを数回踏み、モーターが再学習するのを待つ方法です。
ただし、これでは完全な再調整にならないため、後日必ず専門機での確認を行うことをおすすめします。
警告灯とエラー表示への対処
調整を行わずにエンジンをかけると、メーター内に「EPB故障」や「ブレーキシステム異常」などの警告が表示されることがあります。
これは制御ユニットが正しい基準を持っていないためであり、調整を完了すれば自動的に消灯します。
もし消えない場合は、エラーコードを診断機でリセットする必要があります。
構造理解がトラブル対応を左右する
EPBの本質を理解する
電動パーキングブレーキ(EPB)は、ボタンひとつでブレーキをかけられる便利な装備ですが、モーターと電子制御ユニットで動作する精密機構です。
そのため、電源が途絶えたときやモーターが故障したときに「動かせない」という状況が起こりやすい点を理解しておくことが大切です。
この構造を知っておくだけで、バッテリー上がりや水没といった非常時にも、焦らず正しい手順で対応できるようになります。
手動解除は「知識」と「慎重さ」がカギ
モーターを外し、内部の軸を回してピストンを戻す手動解除は、構造を理解していれば誰でも可能な応急処置です。
ただし、逆方向に回してしまったり、過剰な力をかけると破損につながるため、落ち着いて作業することが重要です。
解除後は必ず輪止めを使い、安全を最優先に行動してください。
再調整を忘れずに
手動解除後は、ブレーキピストンの位置がずれています。
モーターを再装着したら、診断機による「基本調整(初期化)」を行い、電子制御ユニットに正しい基準位置を再登録しましょう。
この作業を怠ると、警告灯が消えない、ブレーキが強く引きずるといった不具合が残ることがあります。
トラブルを防ぐための予防策
EPBのトラブルを未然に防ぐためには、以下の点を意識することが効果的です。
緊急時に慌てないために
いざという時、構造を理解していればトラブルを冷静に対処できます。
電動化が進む現代の車ほど、「仕組みを知ること」自体が最大の備えです。
手動解除の知識と、再調整の重要性を覚えておくことで、あなたの車はより安全に、そして確実にトラブルから回復できるでしょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 電動パーキングブレーキ(EPB)が解除できないとき、最初に確認すべきことは?
まずはバッテリー電圧を確認してください。
EPBはモーター駆動式のため、電圧が下がると解除信号が届かなくなります。
ジャンプスターターなどで電源を一時的に供給すれば解除できる場合があります。
それでも動かない場合は、モーターや制御ユニットの故障が疑われます。
Q2. 手動で解除した後、そのまま走行しても大丈夫?
走行は絶対に避けてください。
手動解除後はピストンが戻ったままで、ブレーキが全く効かない状態です。
車両が転がる危険があるため、輪止めやPレンジ固定で必ず安全を確保しましょう。
移動はレッカーや人力での短距離移動のみに留めてください。
Q3. 手動解除に失敗するとどうなる?
無理な力をかけると、内部ギアの破損やピストン固着を招くおそれがあります。
軸が固く回らない場合は、浸透潤滑剤を少量使うか、専門工場で点検を受けるのが安全です。
軸の形状に合わない工具を使うのもトラブルの原因になります。
Q4. モーターを再装着したのに警告灯が消えません。
警告灯は、基本調整(初期化)未実施のサインです。
診断機でキャリパーの開閉を再設定し、ECUに基準位置を登録する必要があります。
再調整後にエラーコードを消去すれば、警告灯は自然に消えます。
Q5. 水没後でも手動解除は可能?
はい、可能です。
モーター内部が浸水しても、物理的に軸を回してピストンを戻すことはできます。
ただし、配線やセンサーが濡れたまま通電するとショートする危険があるため、応急対応後は必ず整備工場で乾燥処理と点検を受けてください。
Q6. EPBを頻繁に使うと寿命が縮まる?
EPBはモーター制御のため、頻繁な使用による摩耗はほとんどありません。
むしろ、長期間使わないほうが固着リスクが高まる傾向にあります。
日常的に駐車時にEPBを作動させておくことが、モーターとピストンの動きを保つうえで効果的です。
Q7. バッテリー交換後にEPBが誤作動することはありますか?
あります。
電源遮断後は制御ユニットが再起動する際に、位置情報を一時的に失うことがあります。
その場合は、イグニッションONでEPBを数回操作し、再学習させると正常に戻ります。
異常表示が消えないときは、診断機による再調整を行いましょう。
EPBは便利で安全な装置ですが、構造を理解し正しく扱うことが何より大切です。
もし動かなくなっても慌てず、今回紹介した手順を思い出して対応すれば、安全にトラブルを乗り越えることができます。
こちらの記事もおすすめ
- フォルクスワーゲンの異音診断ガイド|原因・修理費用・緊急度
- 走行不良の原因総合まとめ|前に進まない・フラつく・振動する時のチェックポイント
- VW足回りの不調・修理・メンテ総合ガイド|ブッシュ・サス・ベアリング・アライメントの基礎と症状別チェック
▼足回り修理・メンテナンスについての個別ページ一覧▼
車種別の不具合詳細
不具合の“出方”は似ていても、「どのモデルでどんなトラブルが多いか」は車種ごとに少しずつ違います。
車種別の傾向や、他のオーナーに多い故障事例は、以下のページでまとめています。
▼ナイルプラスのサービス詳細▼





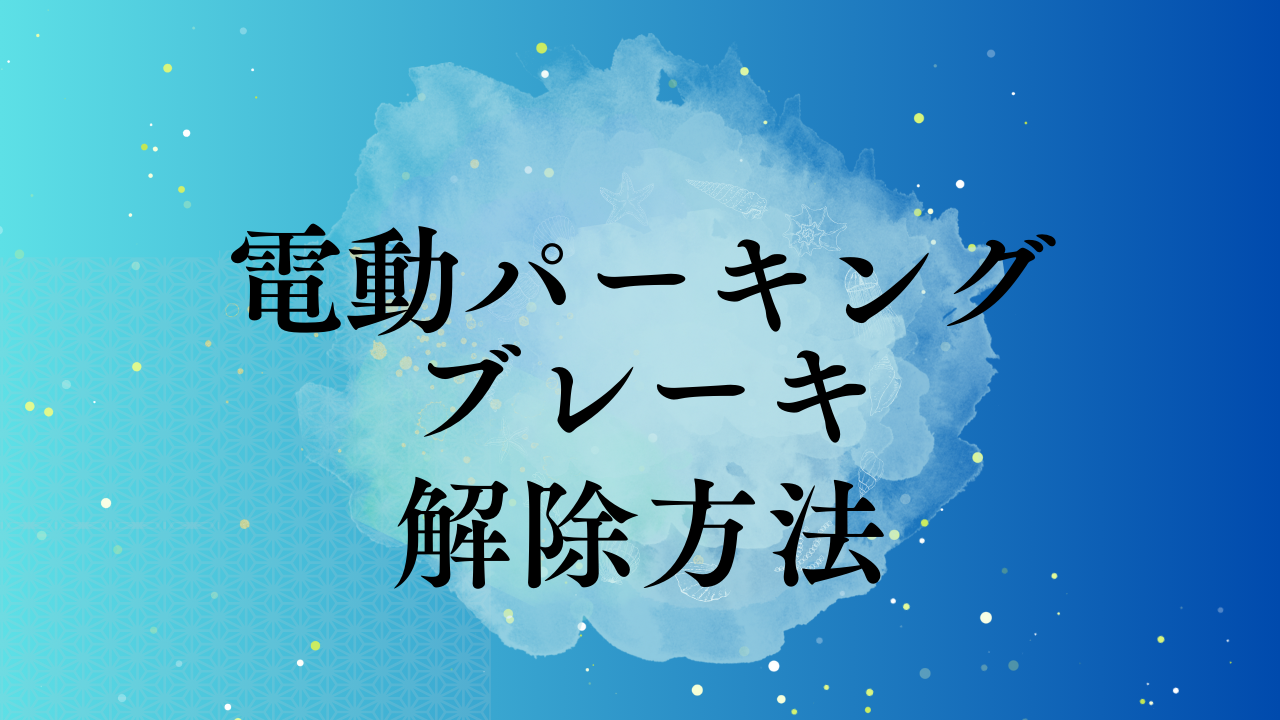
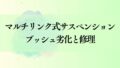
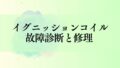
コメント