まずは異音の診断フローをチェック
👉フォルクスワーゲンの異音診断ガイド|原因・修理費用・緊急度
アウディA4〜A6、S7をはじめとする中〜大型モデルや、同系統のサスペンションを持つフォルクスワーゲン車では、フロントサスペンションの異音や振動が発生することがあります。
その多くは「ブレーキ時にドンと音がする」「段差でゴトゴト鳴る」といった症状として現れ、原因はマルチリンク式サスペンションに用いられるブッシュの劣化や損傷である場合が少なくありません。
マルチリンクは操縦安定性と乗り心地を高める優れた構造ですが、可動部が多く、ブッシュの消耗が避けられません。
本記事では、Audi/VW系のフロントサスペンション構造を整理し、ブッシュ交換による再生修理の実際と、高額なアーム交換を避けるコスト最適化のポイントを解説します。
参考リンク:ナイルメカチャンネル「Audi/VW系マルチリンクブッシュ交換と異音対策」
▼ナイルプラスのサービス詳細▼
マルチリンクサスペンションの特徴とメリット
Audi・VW系で採用されるマルチリンクとは
マルチリンクサスペンションは、主にAudiやVWの中・上級グレード車に採用されている高性能な足回り構造です。
フロントに4リンク、リアに5リンクといった独立したアームを組み合わせることで、路面からの衝撃を細かく分散させる仕組みになっています。
通常のストラット式に比べて部品点数が多く、複雑な構造ですが、そのぶん「操縦安定性」と「乗り心地」を高いレベルで両立できるのが大きな特徴です。
独立4リンク構造の仕組み


フロント側では、上部に2本のアッパーアーム、下部に2本のロアアームを配置する「4リンク構造」が採用されています。
それぞれのアームが独立して動くため、タイヤの角度(キャンバー角)が路面状況に応じて最適化され、コーナリング時の安定性が向上します。
また、ブレーキング時にもタイヤがしっかり接地し、ステアリング操作の反応が自然に感じられるのもこの構造のメリットです。
操縦性と快適性の両立
マルチリンクの最大の魅力は、段差やカーブなどの条件が変化しても、タイヤが常に理想的な角度で路面を捉えることです。
結果として、高速道路では直進安定性が高く、街中では乗り心地が柔らかいという相反する性能を両立しています。
これがAudiやVWが「欧州車らしいしなやかな走り」と呼ばれる理由でもあります。
多点可動によるデメリット
一方で、リンク数が多いということは、それだけ可動部分=摩耗する部位も多いということを意味します。
各リンクの接合部にはブッシュやボールジョイントが使われていますが、これらが経年劣化すると、段差通過時に「コトコト」「ゴトゴト」といった異音が発生するようになります。
つまり、マルチリンクは高性能である反面、定期的なメンテナンスを欠かせない構造なのです。
マルチリンクサスペンションは、快適さと安定性を両立させる理想的な仕組みですが、その性能を維持するにはブッシュやジョイント類の点検が欠かせません。
しなやかな乗り味の裏には、複雑な構造と繊細な部品が支えているという点を覚えておくと、トラブル予防に役立ちます。
異音・振動症状からわかるブッシュ劣化の兆候
走行中に現れる「足回りのサイン」
マルチリンクサスペンションを採用するAudiやVW車では、長年乗っていると異音や振動が出てくることがあります。特に次のような症状は、ブッシュ(ゴム製の緩衝部品)の劣化を示すサインです。
こうした症状は、単なる“経年劣化”では済まない場合もあり、足回り全体の快適性や安全性に影響を与えることがあります。
ブッシュが果たす役割


ブッシュは、金属部品の間に挟まれたゴム製のクッションで、振動を吸収し、アームやフレームを保護する役割を担っています。走行中、タイヤやサスペンションが上下に動くたびに、このブッシュがねじれや圧縮を繰り返して衝撃を和らげています。
しかし、長年使用するとゴムが硬化したり、内部に亀裂が生じたりして、本来の弾力を失います。その結果、金属部品同士の動きが直接伝わり、音や振動として感じられるのです。
ブレーキ時の「ドン」という症状
ブレーキを踏んだ瞬間に前方から「ドン」と音がする場合、ロアアームの前側ブッシュが劣化している可能性が高いです。
ブレーキ時に車体が前に沈み込むと、アームが引っ張られ、柔軟性を失ったブッシュが動きに追従できず、衝撃を吸収できなくなります。
段差通過時の「ゴトゴト」音
段差を通過したときに「ゴトゴト」と音が出るのは、アッパーアーム側のブッシュやジョイント部の劣化が考えられます。
上側のリンクはサスペンションの支点として細かく動くため、摩耗しやすい部位です。
初期症状では音が小さいですが、悪化すると振動がステアリングに伝わるようになります。
放置のリスク
ブッシュ劣化を放置すると、足回りの剛性が低下し、タイヤの片減りや直進安定性の低下にもつながります。
音や振動を感じ始めたら、早めに点検を行うことで大きな修理を防ぐことができます。
だから選択肢は3つ
こんなとき、VWオーナーにできる現実的な選択肢は次の3つです。
① まずは診断・見積もり
輸入車に強い整備士が原因を特定し、必要最小限で提案。
② 高額修理の前に査定
整備履歴・社外パーツまでプラス査定の外車専門。
③ 修理費リスク回避の“定額で新車”
車検・税金・メンテ込の月額で故障ストレスから解放。
高額なアーム交換を避ける“ブッシュ打ち替え”という選択

純正交換は高額になりやすい
AudiやVWのマルチリンクサスペンションでは、ブッシュ単体の部品供給がない場合が多く、メーカー純正ではアームごとの交換が基本となります。
1本あたりの部品代はおよそ9万円前後、これが片側で4本、両輪で8本となると、部品代だけで20万円を超えることも珍しくありません。さらに工賃を含めると30万円近い修理になるケースもあります。
このため「異音は気になるけど、修理費が高すぎる」と感じて放置されてしまうことも少なくありません。
ブッシュ単品交換でコストを大幅削減
そこで注目されているのが、“ブッシュ打ち替え”という修理方法です。これは、アーム本体を再利用し、劣化したゴム部分(ブッシュ)のみを新品に打ち替える方法です。
部品代は数千円〜1万円程度、工賃を含めても片側2万円前後で修理可能と、アーム交換の約1/5ほどの費用で済みます。
もちろん、アーム本体が変形していないことが前提ですが、実際にはブッシュだけが劣化しているケースが多いため、費用対効果の高い選択肢です。
打ち替え作業の工程と専用工具の重要性
ブッシュ打ち替えにはプレス機と専用治具が必要です。
まず古いブッシュを抜き取り、圧入方向を合わせて新しいブッシュを挿入します。この際、角度がわずかでもズレるとアームが正しく動かず、再び異音が発生する原因となります。
そのため、熟練の整備士が治具を使って正確に圧入することが重要です。
DIYでの作業は困難なため、信頼できる整備工場に依頼するのが安全です。
👉VW専門店ナイルプラスのメンテナンス・カスタムの費用&作業日数まとめ
打ち替えによる性能の再生
ブッシュを新品に交換すると、アーム本来の柔軟性が戻り、走行中の静粛性やステアリングの応答性が大幅に改善されます。とくに高速道路での直進安定性や、段差通過時の“ゴトゴト感”が解消されるなど、体感できるレベルでの変化があります。
「古いけどまだ乗りたい」「なるべく費用を抑えたい」というユーザーにとって、ブッシュ打ち替えは最適な修理方法といえます。
劣化原因と取付時の注意点
ブッシュが劣化する主な原因
マルチリンクサスペンションに使われるブッシュは、走行中に常にねじれや圧縮の力を受けています。
経年とともにゴムが硬化し、ひび割れが起こるのは自然な現象ですが、環境や使用条件によって劣化スピードが大きく変わります。
代表的な劣化要因には以下のようなものがあります。
特に輸入車はブッシュが柔らかめに設計されているため、国内の路面環境(段差や急停止の多い市街地)では早期劣化しやすい傾向があります。
よくあるトラブル:“1G締め忘れ”による早期破断
ブッシュ交換やアーム脱着時によくあるトラブルが、1G締め忘れです。これは、車両をリフトで上げたままの状態(サスペンションが伸びた状態)でボルトを締め付けてしまうこと。
この状態では、車を地面に下ろしたときにブッシュがねじれた状態で固定されてしまい、走行中に常にねじれ負荷がかかり続けます。その結果、短期間でブッシュ切れやゴム剥がれが発生してしまいます。
正しい1G締めの手順
1G締めとは、車両の荷重がかかった状態でボルトを締め付ける作業を指します。つまり、車をリフトから降ろし、タイヤが地面に接地した状態で締付トルクをかける必要があります。
エアサス車の場合は、リフトアップ時に「リフトモード」へ設定しておかないと、エア量が変化して正しい車高が得られないため注意が必要です。
1G締めのポイントは以下の通りです。
締付け不良がもたらす影響
正しく締められていないブッシュは、走行時に異音や振動を発生させるだけでなく、アーム全体や取り付けボルトにも負荷を与えます。
1G締めを確実に行うことで、ブッシュの寿命が大きく延び、マルチリンクのしなやかな動きを長く保つことができます。
作業手順の概略
エアサス車はリフトモード設定が必須
AudiやVWの上位モデルに多く見られるエアサスペンション車では、作業前に「リフトモード」へ切り替えることが絶対条件です。これを怠ると、リフトアップ中に車高センサーが誤作動し、エア量が変化して車体姿勢が狂ってしまう場合があります。
整備モードに入れてからリフトアップすることで、サスペンションが自然な状態を維持したまま作業できるようになります。
アームの取り外し
ロアアームとアッパーアームを外す際は、ボルトの位置関係と向きを記録することが重要です。AudiやVWのマルチリンクは、アームが交差するように配置されており、1本でも角度を誤るとアライメントに影響が出ます。
また、ボルトやナットは「再使用不可部品」となっているものも多く、伸びや座面変形があるため、基本的には新品に交換するのが安全です。
損傷部の確認とブッシュ圧入作業
アームを取り外したら、まずブッシュの状態を確認します。
ゴムのひび割れ、金属スリーブとの剥離、偏った変形が見られる場合は交換が必要です。
古いブッシュはプレス機で抜き取り、圧入方向と角度を厳密に合わせて新しいブッシュを挿入します。ここで角度がずれると、走行中に異音や早期摩耗を招くため、専用治具を使用して正確に圧入することが求められます。
組み付けと1G締め
新しいブッシュを圧入したアームを元の位置に戻したら、仮止めの状態で車両を地面に下ろします。
このとき、1G状態(車重がかかった状態)で最終トルクをかけるのがポイントです。サスペンションが伸びきった状態で締め付けると、ブッシュがねじれたまま固定され、早期破断の原因になります。
1G締め後は、整備書に記載されたトルク値と角度で再確認し、締付忘れがないか最終点検を行います。
トルク管理の重要性
最後に、トルクレンチを使用して指定トルクを守ることが重要です。マルチリンク構造では1本のボルトが複数の力を受けるため、わずかなトルク誤差が異音やハンドリング不良の原因になります。
締付け後、数日走行した後に再点検を行うことで、ブッシュやボルトの馴染みを確認し、長期的な安定性を確保できます。
アフターケアとコスト比較
アーム交換とブッシュ打ち替えのコスト差
AudiやVWのマルチリンク構造は部品点数が多いため、純正対応ではアームごと交換になるケースが一般的です。
1本あたりの価格は約9万円、フロント片側で4本、両側交換すると20万円を超えることも珍しくありません。
一方で、ブッシュ打ち替え修理を選択すれば、部品代・工賃込みで1本あたり約2万円前後。
つまり、全体で見ても5分の1以下の費用に抑えられます。
アーム本体が再使用できる状態であれば、コストを大幅に節約しつつ、性能をしっかり取り戻すことが可能です。
打ち替え修理後の耐久性
打ち替えブッシュの寿命は、使用する部品の品質と作業精度によって異なります。
純正同等品または高品質社外品を使用し、正確な圧入と1G締めが行われていれば、純正交換とほぼ同等の耐久性が期待できます。実際、再生修理後に5年以上問題なく使用できている例も多く報告されています。
ただし、安価なゴム材を使用した製品や圧入方向を誤った場合は、早期に再劣化する可能性があるため、信頼できる整備工場での施工が前提です。
再発を防ぐためのチェックポイント
修理後も、定期的な点検を怠らないことが大切です。特に以下の3点を確認しておきましょう。
- ブッシュの状態:亀裂や膨らみがないか、ゴムが硬化していないか
- ブーツ類の劣化:破れていると水や砂が侵入し、再劣化を早める
- 1G締め確認:アーム脱着後に正しい姿勢で締付けられているか
また、ペンデュラムサポート(エンジンマウント下部)やアッパーマウントも同時に点検しておくと、異音の再発を防ぐ効果があります。
トータルコストを考えたメンテナンス
ブッシュ交換は一見小さな修理に思えますが、車の安定性や乗り心地に直結する重要な作業です。
早めに対応すれば、他部品への負担を減らし、長期的に見てもトータルコストを下げる効果があります。異音や振動を感じたら早めの点検・修理を心がけることで、車の寿命を大きく延ばすことができます。
👉VW専門店ナイルプラスのメンテナンス・カスタムの費用&作業日数まとめ
マルチリンク車の維持管理の考え方
ブッシュは“消耗品”として扱う
マルチリンクサスペンションは非常に優れた構造ですが、その性能を支えるブッシュは定期交換が前提の消耗品です。
特に欧州車のブッシュは乗り心地を重視して柔らかく設計されているため、路面の段差が多い日本の道路環境では想定より早く劣化する傾向があります。
ゴムのひび割れや硬化が進むと、乗り心地だけでなくタイヤの片減りやアライメントのずれにもつながります。
快適な走行感を維持するためには、5〜7年ごとに一度の交換を目安に考えると安心です。
路面環境と気候による影響
寒暖差の大きい地域や凍結防止剤が撒かれる地域では、ゴムや金属部分の劣化が早く進行します。塩分や湿気によってブッシュ取付部が腐食し、ゴムとの密着が弱まると異音が出やすくなります。
雨の日や冬季の走行後は、車体下部を軽く洗い流すなど、サスペンションまわりの防錆ケアを意識することも長寿命化のポイントです。
定期的なリフト点検の重要性
異音やガタつきは、車を上げて下から確認しないと分からないことが多いです。
ディーラーや整備工場での半年〜1年に一度のリフト点検を習慣化することで、ブッシュの初期劣化やジョイントの緩みを早期に発見できます。
とくに「ゴトゴト音がする」「ハンドルが軽すぎる」「車がまっすぐ走らない」といった変化を感じたら、早めの点検が効果的です。
1G締め確認の徹底
マルチリンク車のメンテナンスで忘れてはいけないのが1G締めです。どんなに高価な部品を使っても、締付け姿勢が正しくなければ早期劣化を防ぐことはできません。
車重がかかった自然な姿勢でボルトを締め直すだけでも、ゴムのねじれを防ぎ、走行時のしなやかさを長く保てます。
特に車高調整を行ったあとは、必ず1G締めを再確認しておくことが重要です。
維持のコツ
マルチリンク車のしなやかな乗り味は、こうした地道なケアによって保たれます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 段差を越えたときに「ゴトッ」と音がします。どの部品が原因でしょうか?
最も多いのはロアアームやアッパーアームのブッシュ劣化です。ゴム部分が硬化して動きに追従できなくなると、金属部品同士の衝撃が音として出ます。放置すると他のジョイント部にも負担がかかるため、早めの点検をおすすめします。
Q2. ブッシュ打ち替えは安全面で問題ありませんか?
正しく作業すれば純正交換と同等の安全性が得られます。重要なのは、圧入方向や角度を正確に合わせることです。プレス機や治具を使いこなせる整備工場に依頼すれば、安心して再生修理が可能です。
Q3. ブッシュだけの交換で、乗り心地はどの程度変わりますか?
新品ブッシュに交換すると、走行中の振動や突き上げが大幅に減少します。ステアリング操作も軽くなり、直進時の安定感が向上します。特に劣化が進んでいた車ほど違いが分かりやすいでしょう。
Q4. DIYでブッシュ交換はできますか?
ブッシュは圧入式構造のため、プレス機や専用工具が必要です。圧入方向を誤るとアームが歪み、走行中に異音が再発する可能性があります。そのため、DIYでの作業はおすすめできません。
Q5. エアサス車で注意すべき点は?
エアサス車では、リフトアップする前に必ずリフトモードを設定してください。これを怠ると車高センサーが誤作動し、足回りの姿勢が崩れる可能性があります。また、締付け作業は1G状態(車重がかかった状態)で行うことが必須です。
Q6. 打ち替え後の耐久性はどれくらいですか?
高品質な純正同等品や強化ブッシュを使用すれば、5〜8年程度の耐久性が期待できます。使用環境や走行距離によって前後しますが、適切な締付けと定期点検を行えば長期間性能を維持できます。
Q7. 異音が再発する原因は?
多くの場合、1G締め忘れやトルク管理ミスが原因です。また、他のジョイント部(ボールジョイントやスタビリンクなど)の劣化も関係することがあります。修理後に再発した場合は、足回り全体を総合的に点検しましょう。
Q8. コストを抑えながら確実に修理したいのですが?
費用を抑えたい場合は、ブッシュ打ち替え+信頼できる整備工場の組み合わせが最も効果的です。純正アームを再利用できれば、20万円クラスの修理を2万円前後に抑えられます。
異音の原因を正確に診断し、必要最小限の部品交換で済ませることが、コストパフォーマンスの高い整備のポイントです。
異音や乗り心地の変化は、マルチリンクサスペンションが発する“メンテナンスのサイン”です。早めに点検し、正しい修理を行うことで、愛車の快適な走りを長く保てます。
こちらの記事もおすすめ
- フォルクスワーゲンの異音診断ガイド|原因・修理費用・緊急度
- 走行不良の原因総合まとめ|前に進まない・フラつく・振動する時のチェックポイント
- VW足回りの不調・修理・メンテ総合ガイド|ブッシュ・サス・ベアリング・アライメントの基礎と症状別チェック
▼足回り修理・メンテナンスについての個別ページ一覧▼
車種別の不具合詳細
不具合の“出方”は似ていても、「どのモデルでどんなトラブルが多いか」は車種ごとに少しずつ違います。
車種別の傾向や、他のオーナーに多い故障事例は、以下のページでまとめています。
▼ナイルプラスのサービス詳細▼





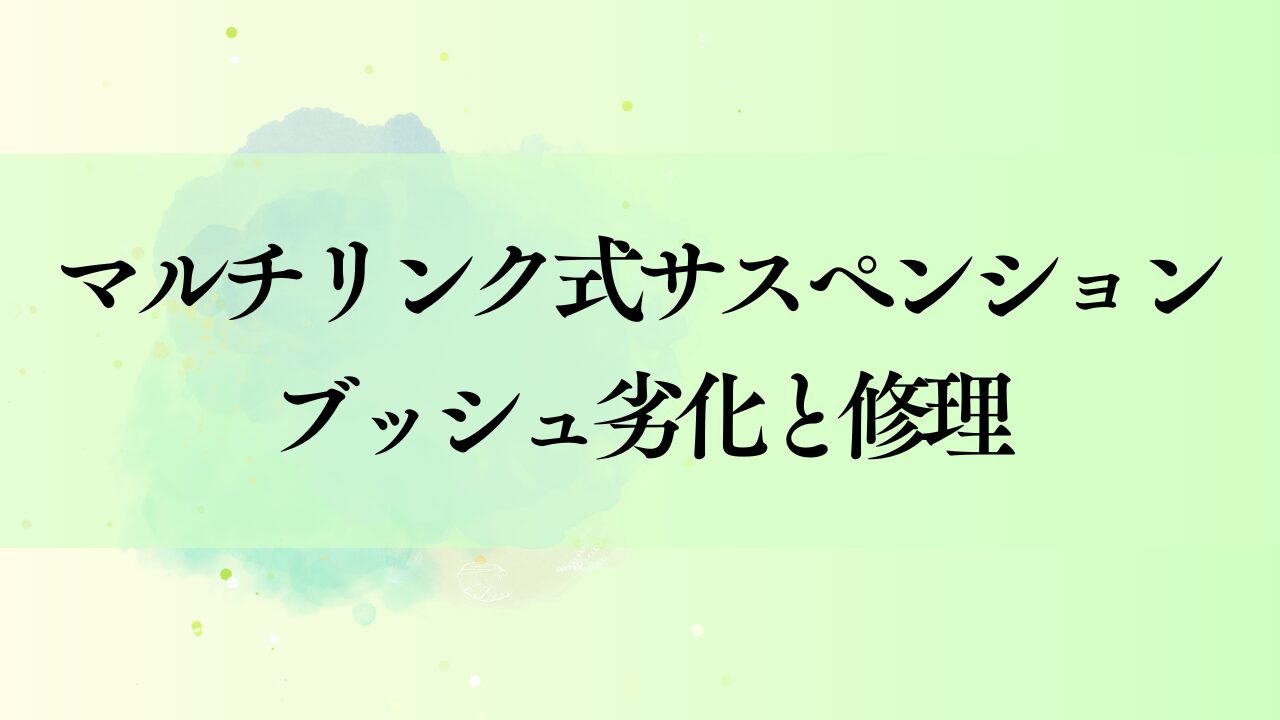
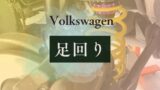
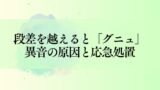
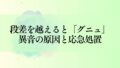
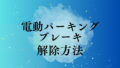
コメント